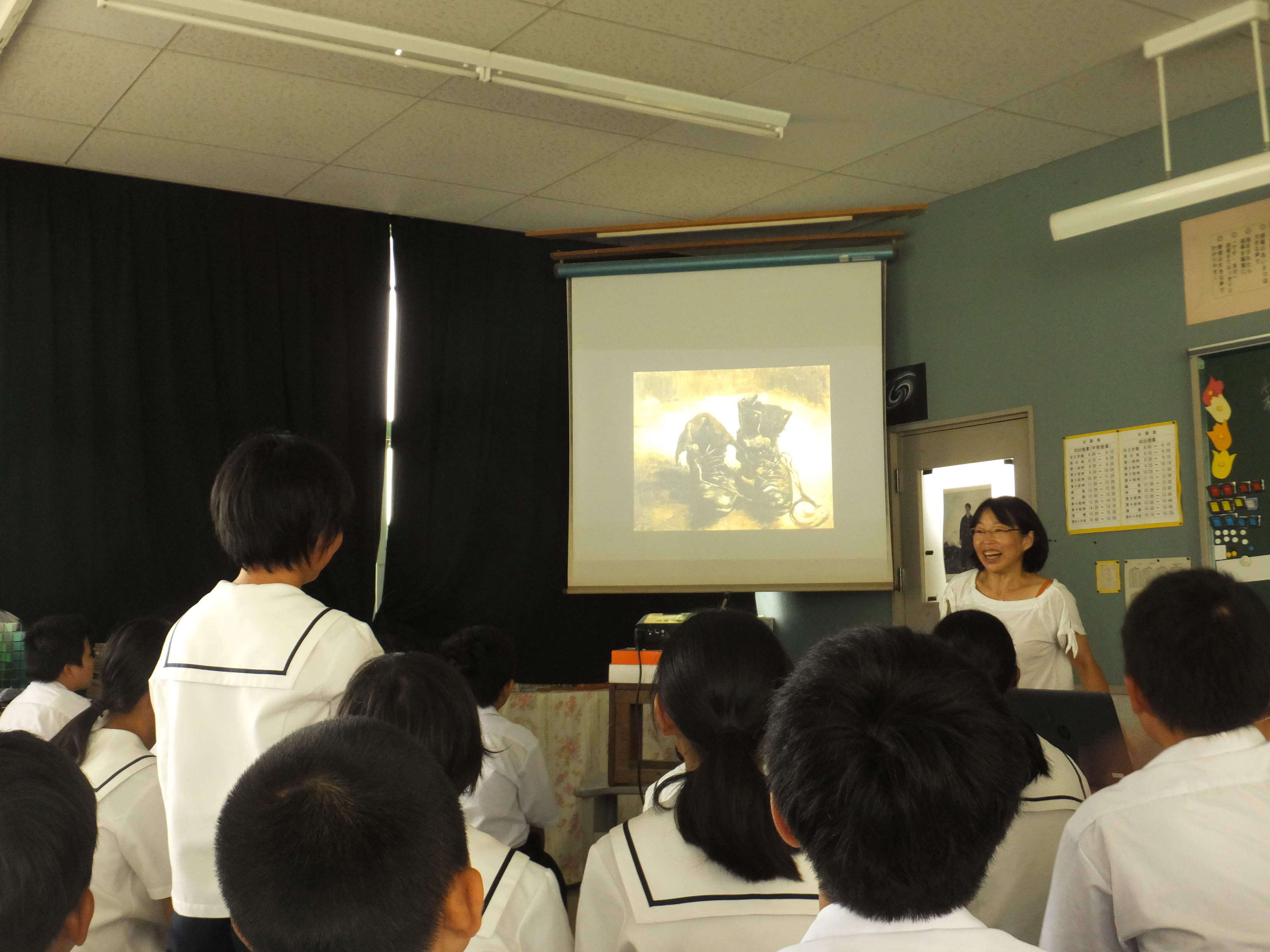イエメンは、コーヒーの発祥の地と言われています。
この国のモカ港を出発点にして、世界にコーヒーは広がっていきました。
しかし、そういった輝かしい歴史があるにもかかわらず、今、この国では、内戦状態が続き、豆の輸出が困難な状況にあります。
一人当たりのGDPによると、イエメンは、449ドルという、世界でワースト5位です。
2020年5月、コロナ禍の時に、日本在住イエメン難民の妊婦さんから、私のところに、生活資金が足りないので自宅出産を考えているどうしたらいいのでしょうか?という相談がありました。そこで、彼女の出産費用を捻出するためにイエメンコーヒーを販売したことをきっかけに”Save Yeman Babies”は、歩み始めました。
一人でも、多くの方にご支持いただければ幸いと存じます。
Save Yeman Babies 代表 大川理恵
Life Story

保育園の頃の夢
保育園の初めての誕生日会では
「大人になったら、何になりたい?」
と保育士さんが誕生日を迎えた子みんなに聞いていました。
私の番になった時、
「大人になったら、絵の先生になりたいです!」
と答えたのを今でもはっきりと覚えています。
自分で絵をろくに描けてないうちから、絵の先生になりたいって、笑っちゃいますよね。
だけど、その4歳ぐらいの私は、真剣に思っていました。

デッサンに勤しむ一方で…
小学生の時トランペット鼓笛隊というのに入っていた流れで、中学、高校と吹奏楽部に入りました。
だけど、将来の進路は、幼児期から思っていた「絵の先生」になりたかったので、高校3年の時に、最後の大会も出ず、部活を辞め、受験のためのデッサンに勤しむようになったのでした。
ただ、最後の大会に出なかった私はなんとなく吹奏楽部を、「燃え尽きずに辞めてしまった」という心残りができてしまいました。
そして、この時の心残りは現在の難民支援を始めるに至るまで長く尾を引いてしまうことになるのでした。

きっかけと挫折の大学生活
大学は教育学部の美術課程に進学しました。高校の時に、「熱くやり遂げたかった」という心残りがあった私は再び音楽の世界に触れるべく、オーケストラサークルに入りました。
そして、同時に「障害者問題を考える会 view」という同好会にも入りました。この「障害者問題を考える会 view」という同好会がその後に大きく影響してくるとは当時の私は思ってもないことでした。

無事、美術を専攻する大学の学部に入ることができ、
「おお、これで、絵の先生になれる道に近づいた」
と思ったのですが、大学4回生の時に受けた教員採用試験に合格することができませんでした。
卒業年にどこにもいくところがなかったため、半年間、研究生として大学に籍を置きながら、次の年の採用試験にもう一度チャレンジすることにしました。
しかし、またもや、試験に合格することはできませんでした。
二回の試験の失敗でやけになった私は、家から徒歩5分のところにある造園の会社に行き、就職することを決めました。
(*造園会社の方々には、大変お世話になっていました。このような表現ですみません。だけど本当に自暴自棄になっていた時期だったと思います。そんなわたしを雇っていただき誠に感謝しております。)
人生を変えるスリランカ人との出会いとはじめての一人旅
その造園会社で働く中で、あるスリランカからの研修生に出会いました。
その方から聞く、異国の話がとても面白くて、その方の研修期間が終わる時に
「私も、スリランカに行ってみていいですか?」
と聞いてみると、
「いいよ」
と快諾してくださったので、会社も辞め、飛んで行きました。
それは、一ヶ月半の初めての一人旅だったのですが、とても楽しかったです。英語は得意ではありませんでしたが、片言の英語でも、何とか旅はできました。しかし、一ヶ月も旅を続けて現地の人と触れ合う中で、英語ではなく、その国で喋られている母国語を喋った方が、もっと「仲間」に入っていけると感じました。
そんな風に感じていた時、偶然、電車の中で隣に居合わせた現地のスリランカ人から、
「シンハラ語が上手い日本人知ってるんだよ。君、会ってみるかい?」
と言われて、自分の感じたことが正しいかどうか確かめたいという好奇心で会いに行きました。
残念ながら、その日本人には、会うことができなかったのですが、会いに言った先の薬草園で、「JICA」という文字を見つけました。
私は、その文字を見た瞬間に、「ここって、青年海外協力隊の活動場所だったのかもしれない」と思いました。
難民支援につながる自分自身への気づき
その後、日本に帰ってから、青年海外協力隊を目指しました。その時、募集要項に2年の実務歴があった方がいいと書かれてあったので、えひめ子どもの城で、児童厚生員として2年間働きました。
そして、期間が終わる年に、青年海外協力隊の試験を受けてみると、合格することができたのです。
私は最初、自分の任地はスリランカのような緑あふれる国だろうとイメージしていました。ところが、実際の任地は「エジプト」。
エジプトと聞いて
「一体、何なの?エジプトって?ほとんど砂漠やん、怖い怖い。」
と感じました。
エジプトでの任務は障害児施設にて、知的に障害を持っている子どもたちに美術を教えることで、私が大学生の時に入っていた同好会での経験が、ここで活きてくるとは、予想もしてないことでした。
現地語もだいぶ話せれるようになったころ、
ふと「私は、いままでずっと寂しがり屋だったのかもしれない」と思いました。
それが、はっきりとわかったのは現地で同僚の先生に誘われて、カイロの街中で紅茶を飲んだ時の出来事がきっかけでした。
紅茶を飲み終わり、帰る時間になったとき、私は家への帰り方が分からないことに気づきました。
カイロという慣れない町で
「ここで解散してしまったら、どうやって家に帰ったらいいのだろう」
という不安が押し寄せ、一人困っていた時、一緒に紅茶を飲んでいた先生は
「ここで、あなたを見捨てる(置いて帰る)はずはないだろう」
といって、家まで直通のバスに乗せてくれ、私は家まで無事たどりつきました。
たわいのない出来事なのですが、私にとって、この時の出来事はかなり心の深いところに突き刺さったのでした。
それはきっとこの時に感じた何気ない「私は一体これからどうすればいいのだ」っていう問いに初めて答えてもらった経験だったからです。
振り返ってみると、私は幼少期から、ずっと「どうすればいいのか」という問いに何度もぶつかってきていたものの、今までこの問いを答えてくれる他人には出会うことなく、気づけば大人になっていたのでした。
しかし、その「どうすればいいのか」という問いに答えてくれた人に初めて出会ったとき、これまでは他人にとっては何でもない疑問や不安を抱いても、誰も答えてくれないから、1人で頑張ってきただけであって、 誰か答えてくれたら勇気100万馬力なのだ。ってことが、はっきりわかった瞬間だったのです。
シリア難民の支援
協力隊の任期が終わり、日本に帰った後、公立中学校の講師として、美術を教えはじめました。そして、しばらくして、独立し、自分で美術教室を立ち上げました。
やっと「絵の先生」になれたと思いました。
自分の夢も叶い、忙しく毎日を過ごす中で、語ることもなくなったエジプトの記憶がだんだんと遠のいていっていた2015年ごろ。
松山に、シリア難民のご一家が通訳を必要としていると一報入ったことから、私の眠っていた記憶が呼び覚まされました。
もう、10年以上、アラビア語も喋っていなかったので、忘れているんじゃないかと思いきや、全然そんなことはなく、昨日のことかのように、出来事と言葉とがリンクして思い出が溢れ出てきました。
そして同時に寂しさを感じてながらも他人に助けを求めることができなかった自分。でもいつも助けを待っていたという過去の自分の姿とこのシリア人が重なったのでした。
わたしの思い込みかもしれないのですが、このシリア人は、きっと、あの時の私のように”一体、どうすればいいのだ”っていう疑問を抱えたまま、日本で生活しているのではないか?と思いました。
ほんのちょっとしたことでも、彼らの疑問に答えてあげることによって、彼らの居場所を作ってあげられるのではないか?彼らを安心させることができるのではないか?
そう思った私は、彼ら難民のサポートをすることに決めました。
-
アトリエを立ち上げたとき
-
学校で美術教員をしていた時
-
アハマッド君の急病で、元旦に入院してた時
-
地元農業高校の生徒たちとシリア料理を作る
イエメン難民の支援
そして、2020年、コロナ禍で、緊急事態宣言は出ていた5月、イエメン難民の方から、連絡が来ました。
彼女は、1年前に日本に難民としてきたイエメン人で、ご夫婦でこられていました。難民申請をしていましたが、申請は認可されておらず、仮放免として暮らしていらっしゃいました。そんな中、妊娠されて、どうやって産んだらいいのか?保険証も作ることは許されなかったので、自力で産まないといけないと考えた彼女は、「自宅出産」をしようと考えていたのです。
命に関わることだったので、初産だし何かあってからでは、いけないと思い、出産費用が必要なことで、この問題が解決するのであったら、出産費用を何が何でも集めようと思いました。
それが、このイエメンコーヒーを販売することだったのです。
最初はイエメンコーヒーを売ろうと思っても、誰から仕入れたらいいのだろうと、全く見当もつかなかったのですが、検索してみると、意外とあっさり見つかりました。イエメン人が設立したコーヒー卸会社が日本にあって、その代表の方と話してみると、話しやすい方だったため、ここと取引することにしました。
その方がモカオリジンズのタレックさんです。
8月から本格的に販売をし始めたのですが、一挙に売り上げが上がり、無事、イエメン夫婦に10万円を送ることができました。そして、8月23日に無事元気な男の赤ちゃんが誕生しました。
Save yemen babiesの立ち上げ
イエメン難民の夫婦に出産費用を用意することができ、彼女たちへの支援は終わっかたかなあと思いました。
いえ、終わってはいなかったのです。
根本にある問題は、「なぜ、難民が、次から次へと発生するのか?」を考えなきゃいけないのだと思います。
イエメンは、とても風光明媚なところなのに、国内紛争がずっと続いています。
国民は、世界中に散らばって、何とか生きている状況です。
私が、取引しているイエメンコーヒーは、イエメン100%のコーヒー豆です。
コーヒーを少しでも購入することによって、この国の農家さんの生活の安定が図られるのならば、そのまま継続して、販売を続けるべきだと考え、コーヒーを販売する時にパッケージにつけていた「Save Yemen Babies」を組織名として販売するシステムを作ってみることにしました。
こうしてできたのが「Save Yemen Babies」です。
今後の目標
このコーヒーの売り上げは、現地で生産している農家さんのマイクロファイナンスの一部として、使ってもらいたいと考えています。そして、中東の夢を持った起業したい方への、夢実現のための資金の一部として寄付ができる基金にもしていきたいと思っています。もちろん、日本在住イエメン難民の方への支援も続けていきます。
小さなところから、大きなところまで、小回りの効く基金を作りたいというところが、目下、具体的な目標です。
そのために、皆様、どうかご協力よろしくお願いいたします。